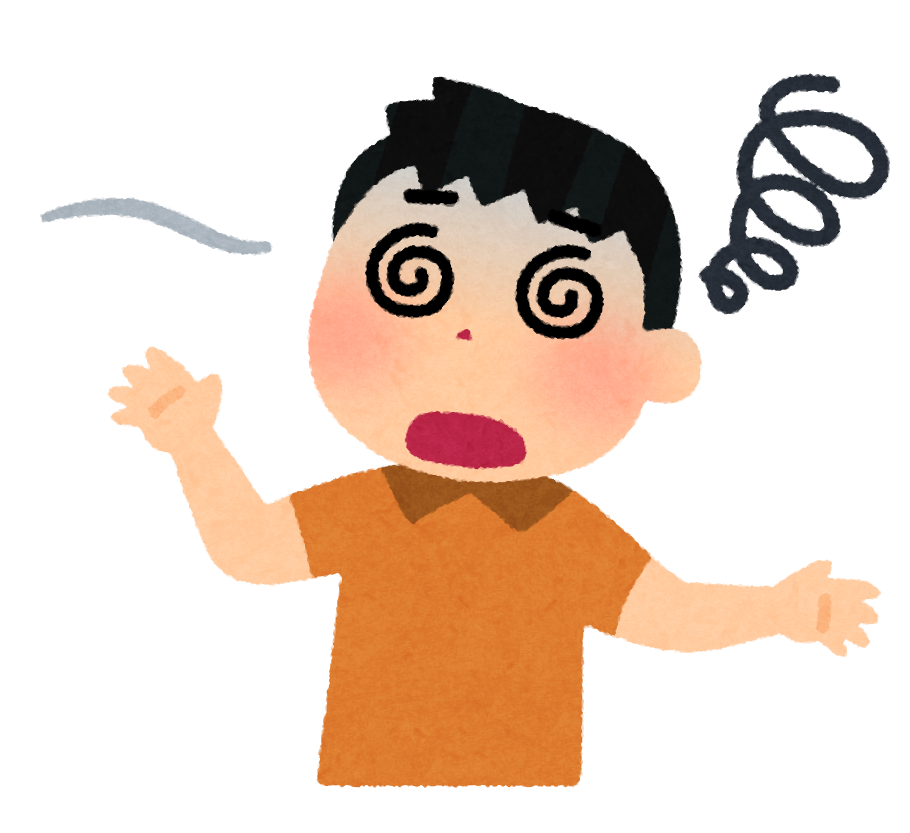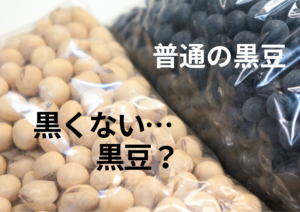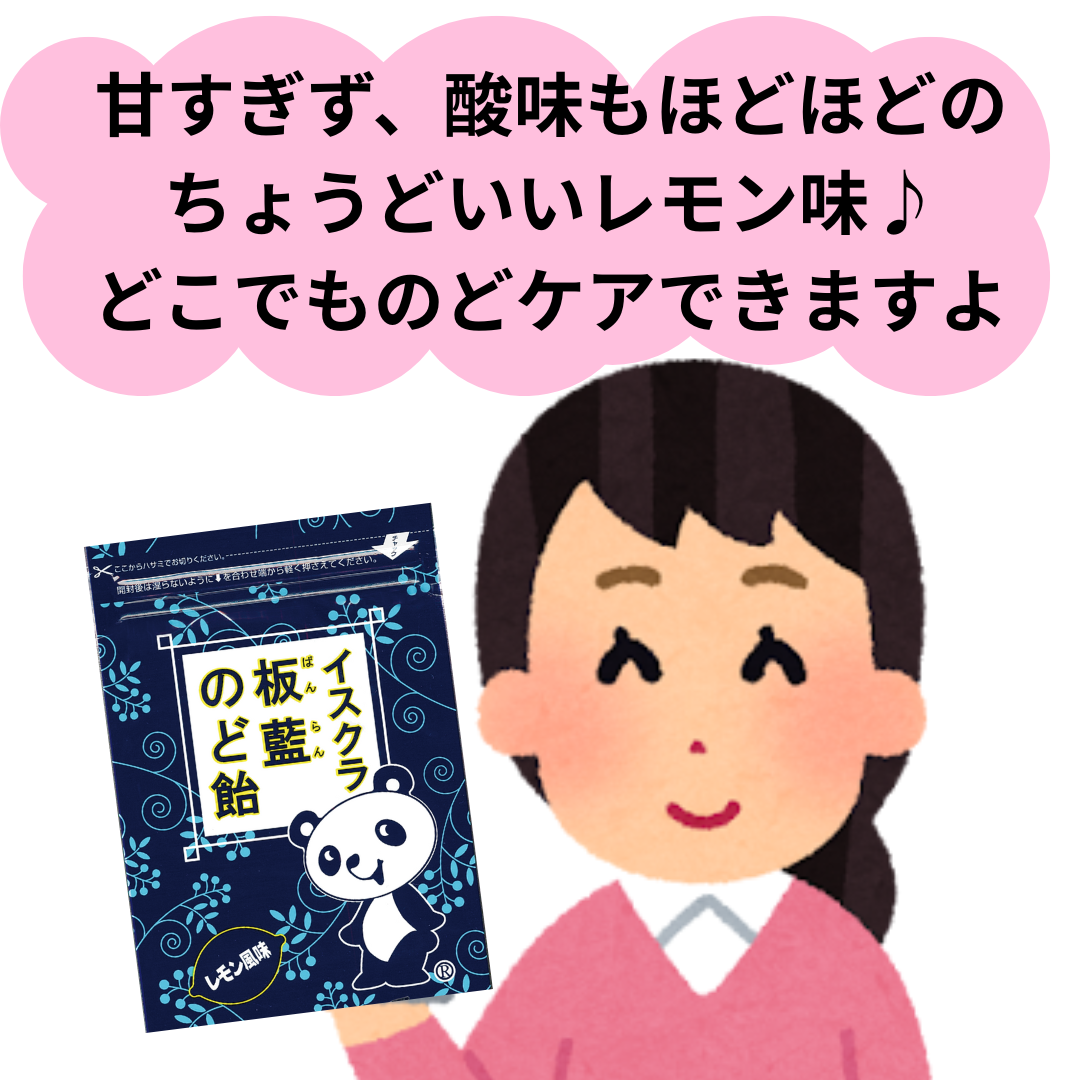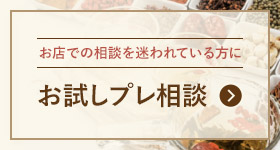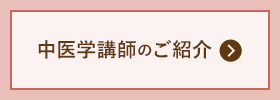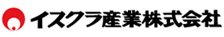こんにちは、丹沢です。
今回は「めまい」について、現代医学的に考えていきます。
【めまいの分類】
めまいは、どの部位に原因があるか、またどのような症状として現れるかによって分類されます。
大きく分けて「前庭性めまい」と「非前庭性めまい」の2種類あります。
・「前庭」とは?
耳の奥にある平衡感覚を司る部分です。
身体のバランスに深く関わっており、ここにトラブルが生じるとめまいが起こりやすくなります。
【前庭性めまい】
前庭性のめまいは、「末梢性」と「中枢性」に分けられます。
症状の現れ方としては、回転性(ぐるぐる回る感じ)と非回転性(ふわふわ浮く感じ)があります。
・末梢性めまい(主に回転性)
→前庭の末梢部位、つまり内耳や前庭神経に原因があります。
≪主な原因≫
・メニエール病:「内リンパ水腫」により蝸牛が圧迫されることによっておこります。
・乗り物酔い(動揺病):前庭や三半規管への反復する加速度刺激によっておこります。
・中枢性めまい(回転性めまい・非回転性めまい)
→中枢神経系(脳血流障害)に原因があります。
≪主な原因≫
・脳梗塞
・脳内出血
・薬剤性
・アルコール
など
【非前庭性めまい】(非回転性めまい)
→前庭とは関係なく、血圧や心臓、精神的要因などで起こるめまいです。
≪主な原因≫
・起立性低血圧
・貧血
・低血糖
・高血圧
・心因性(心身症、うつ病)
・更年期障害
・眼精疲労
・不整脈
など
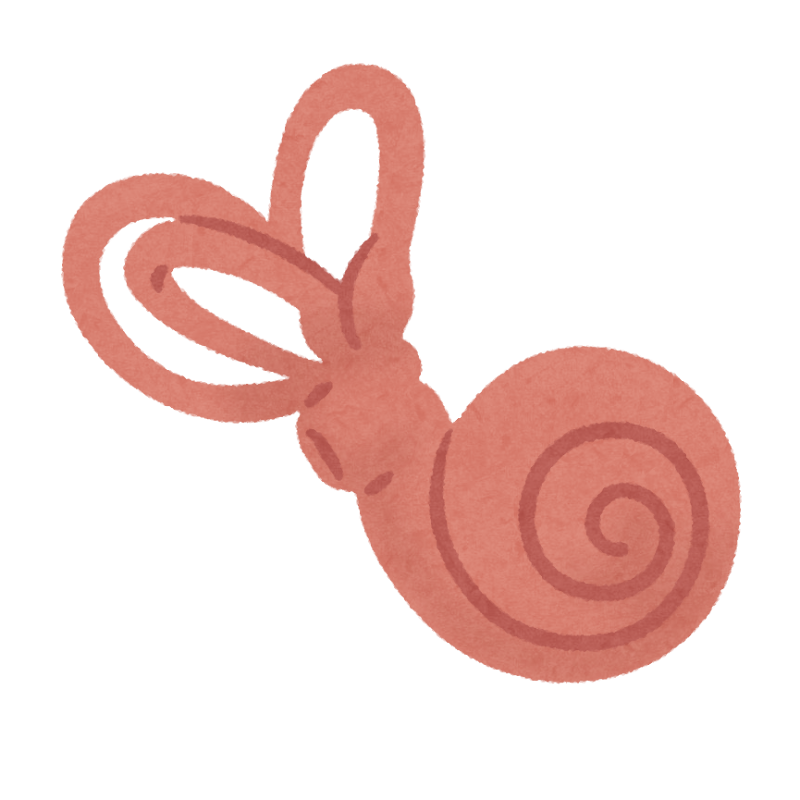
【まとめ】
「めまい」と一言で片づけるのではなく、その背景には現代医学的にも、中医学的にも、多様な原因やタイプがあります。
原因や体質に応じた正しい理解と対応が重要です。
次回は、中医学的な視点から見た「めまい」についてご紹介します。
どうぞお楽しみに!